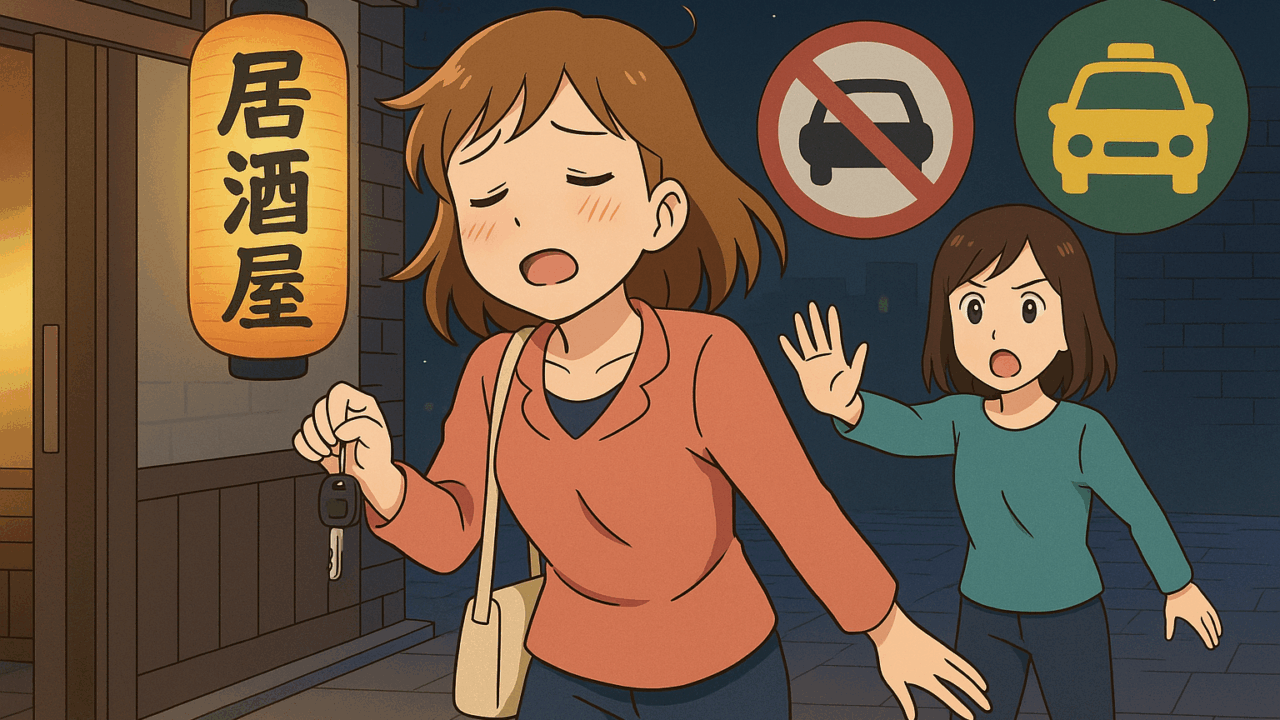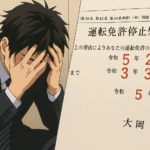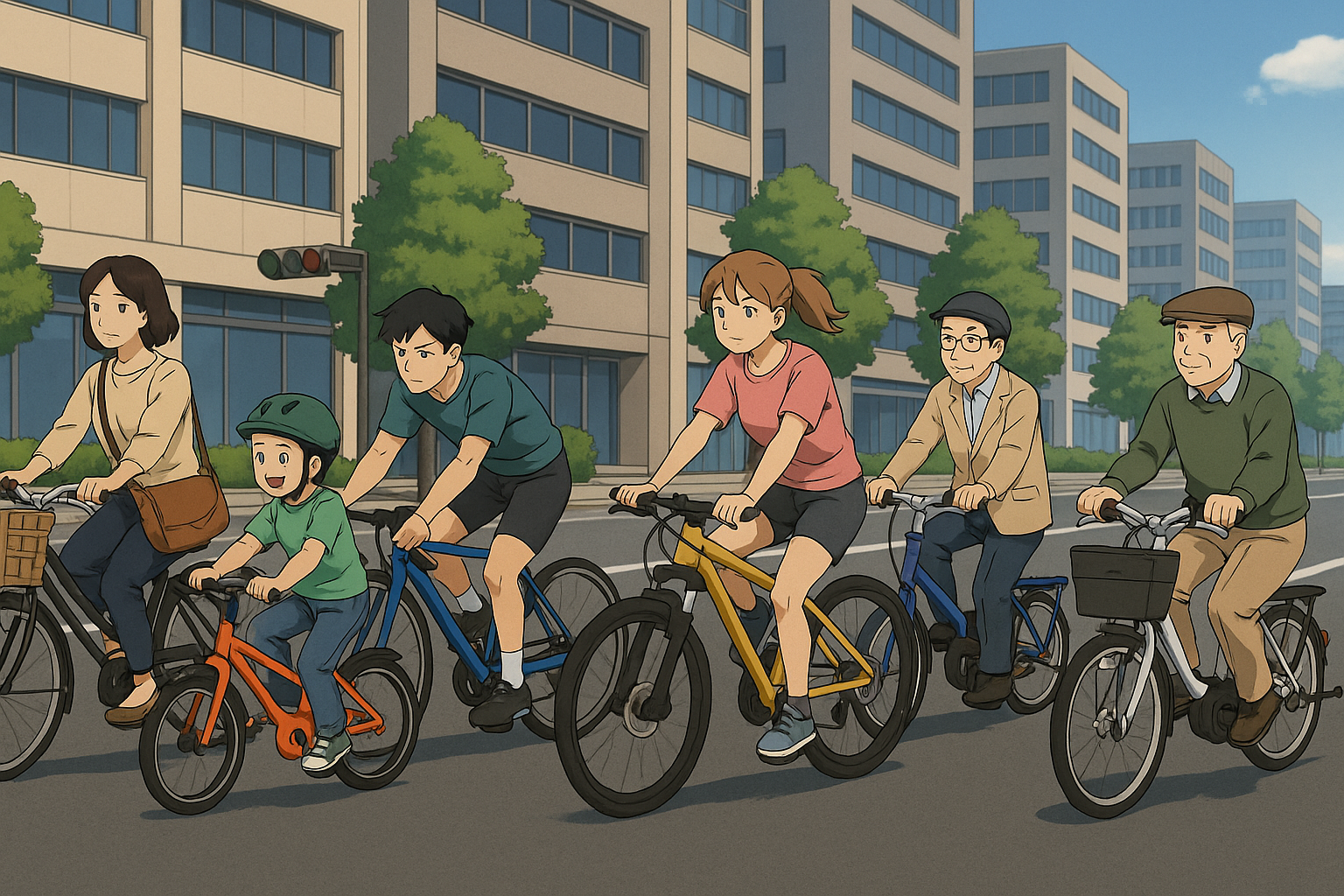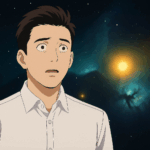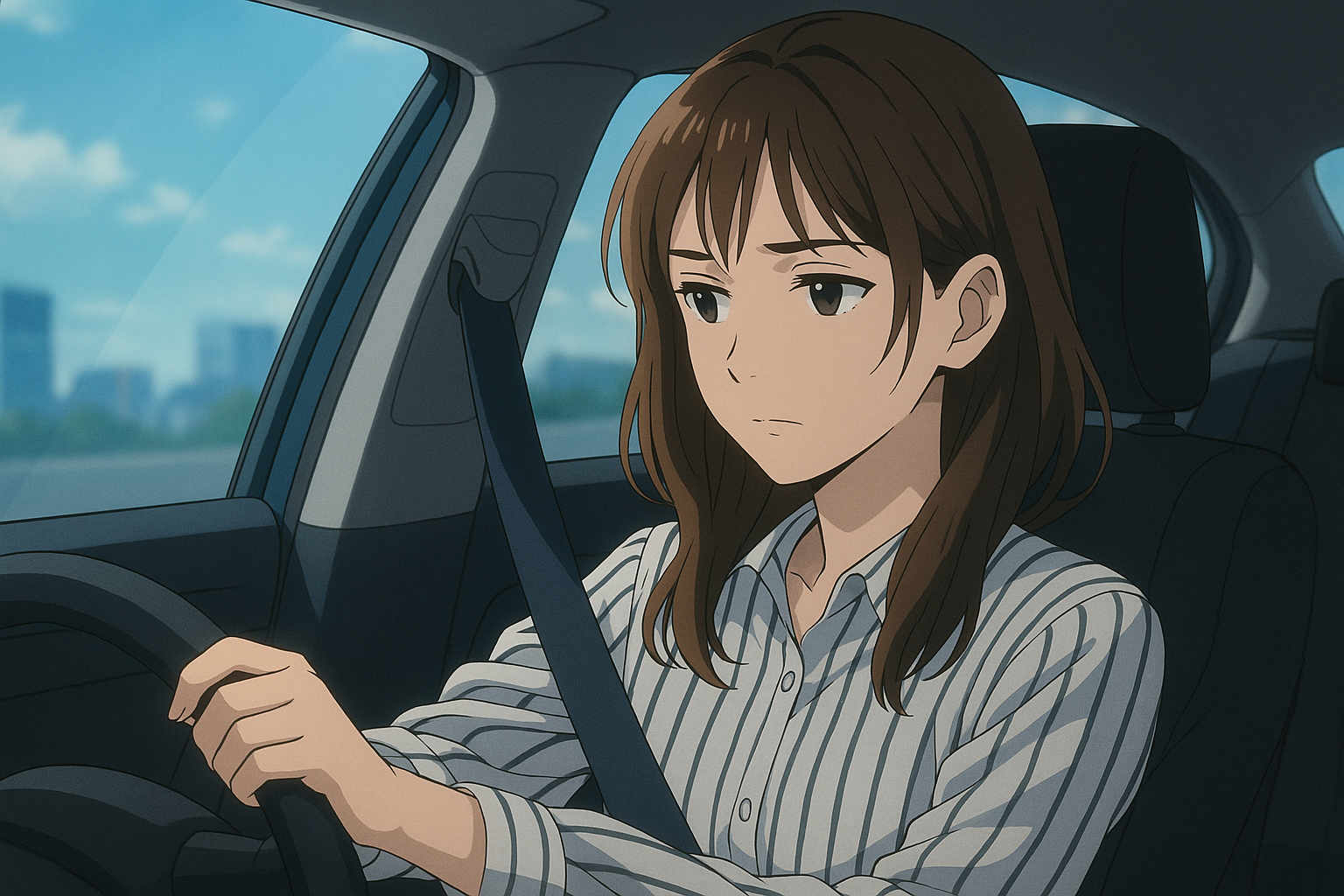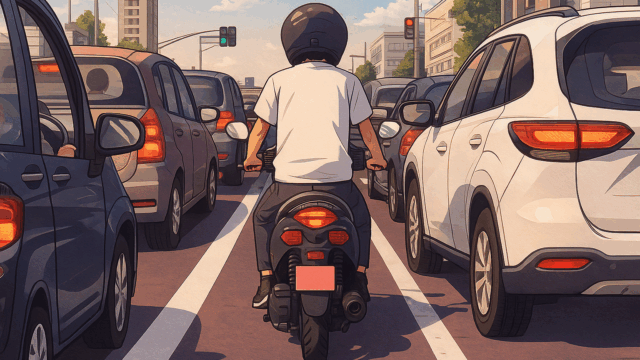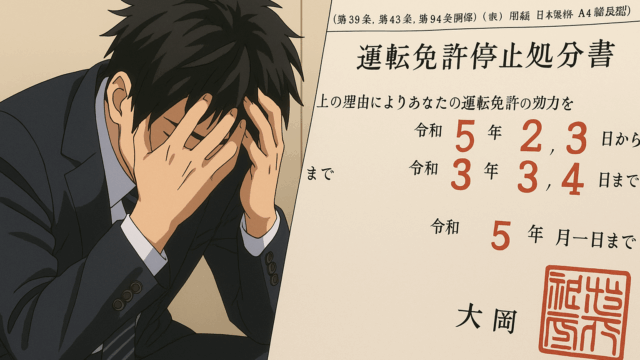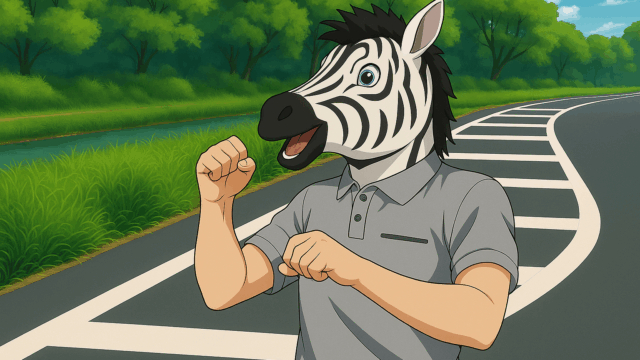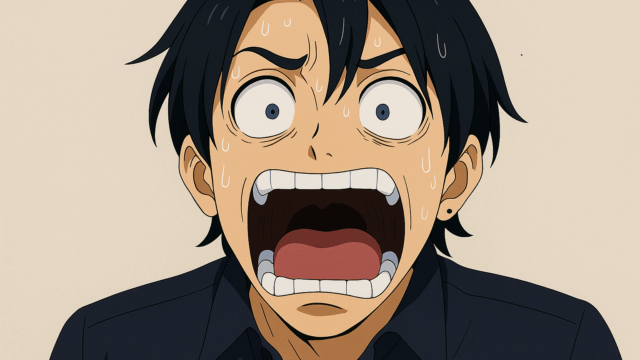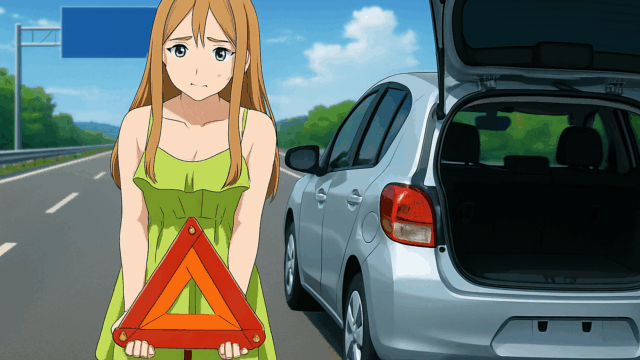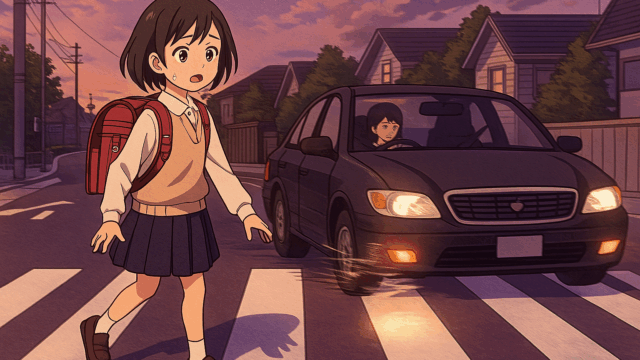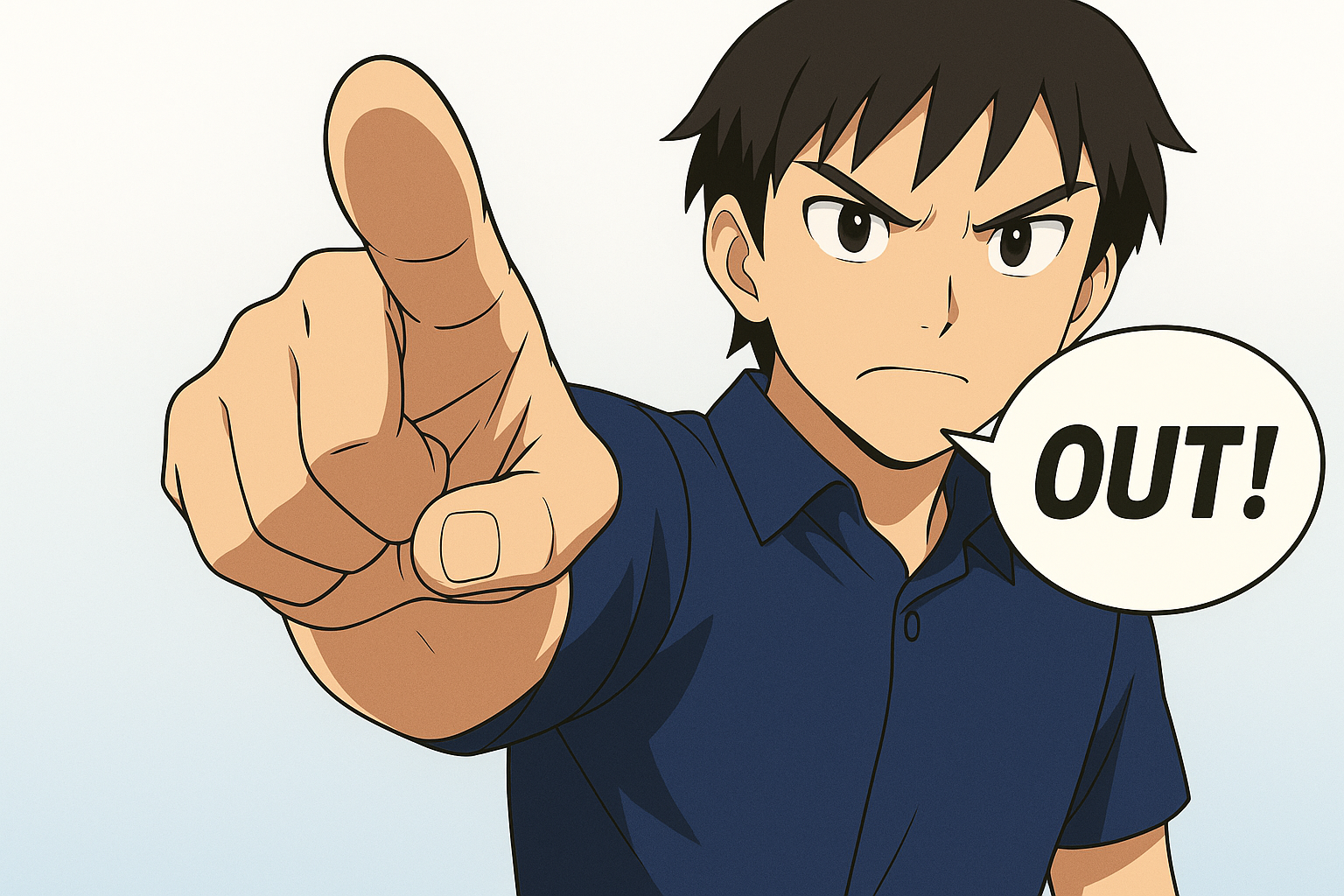警察の検問で使われるアルコール検知器の基準は呼気1リットルあたり0.15mg。
本記事では、飲酒運転の分類、0.15mgの意味、罰則、体格差の影響、翌日残り、検問の流れ、事故リスクと防止策までを一般向けに解説します。
飲酒運転の二つの分類
道路交通法上、飲酒運転は次の2種類に分かれます。
- 酒気帯び運転:呼気1リットルあたり0.15mg以上が検出、または外観・挙動から酒気帯びと判断。
- 酒酔い運転:数値に関係なく、アルコールの影響で正常な運転ができない状態。
酒気帯びは数値、酒酔いは状態が判断軸です。
0.15mgの意味と超えやすい量
呼気0.15mg/L ≒ 血中0.03%程度に相当し、反応・判断力の低下が有意に出始めるラインです。
- ビール中瓶(500ml)1本 → 0.15mg前後に到達する人が多い
- 日本酒1合(180ml) → 0.15mg超の可能性あり
- チューハイ350ml(7%)1缶 → 体格次第で基準超え
「缶ビール1本なら大丈夫」は通用しません。
性別・体格・体調で変わる影響
- 女性は分解酵素が少なめで影響を受けやすい。
- 体重が軽いほど少量で基準超えしやすい。
- 空腹・疲労時は吸収が早く数値が上がりやすい。
同じ量でも個人差が大きいため、「量」で基準を推し量るのは危険です。
アルコール分解スピードの目安
- 成人男性(60kg)で1時間に約5〜7g分解。
- ビール中瓶1本(約20g)→ 3〜4時間必要。
- 日本酒1合(約20g)→ 同上。焼酎ダブル1杯(約25g)→ 4〜5時間以上。
深夜まで飲んだ翌朝は、まだアルコールが残っている可能性が高いです。
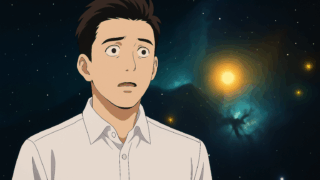
酒気帯び/酒酔い運転の罰則
酒気帯び運転(0.15mg以上)
- 違反点数:13点(免停90日)
- 刑事罰:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒酔い運転(状態で判断)
- 違反点数:35点(即取消・欠格3年)
- 刑事罰:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
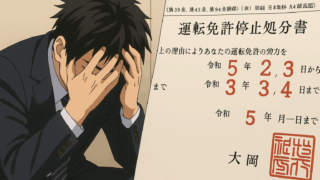
検問の流れとよくある誤解
流れ
- 会話で酒気を確認(匂い・挙動)。
- 疑いがあれば簡易検知器。
- 反応が出たら正式測定器で数値を記録。
よくある誤解
- ノンアルでも反応? 一時的反応はあり得るが、基準超えに至ることは通常ない。
- 口に含んだだけでアウト? 一時的高値が出るため、検査前の飲食は控える指導。

翌日でもアウトになる理由
- ビール3本 → 7〜8時間残存。
- 日本酒2合 → 10時間以上残る可能性。
- 焼酎5杯 → 翌日午前中でも基準超の恐れ。
「寝たから大丈夫」は誤解。通勤中の検問で発覚する例も多いです。
事故リスクと統計のポイント
飲酒運転事故は死亡率が高いのが特徴。
- 飲酒運転事故の死亡率:約8%
- 全交通事故の死亡率:約2%
死亡率はおよそ4倍。自分も他者も守るため、飲酒運転は絶対にしないこと。
飲酒運転を防ぐ方法
- 代行運転を利用(数千円で安全を確保)。
- 公共交通を選択(終電・バス時刻の事前確認)。
- タクシー/配車アプリを活用。
- 仲間内で「飲んだら運転しない」を徹底。
まとめ
- 飲酒運転は酒気帯び(0.15mg以上)と酒酔い(状態)に分類。
- 0.15mgは血中0.03%程度。ビール1本でも超える人がいる。
- 性別・体格・体調で影響大。翌朝も残ることがある。
- 罰則は重く、事故の死亡率は約4倍。防止策を準備して飲む。
参考:警察庁 交通安全情報
よくある質問
Q. アルコールが強い自覚があれば運転しても大丈夫?
A. NGです。代謝が早くても判断力低下は避けられません。数値を超えれば酒気帯び成立です。
Q. ノンアルコール飲料で検知される?
A. 一時的反応はあり得ますが、基準超えに至ることは通常ありません。検査前の飲食は避けましょう。
Q. 翌朝の出勤時、どのくらい空ければ安全?
A. 量・体格次第です。ビール中瓶1本でも3〜4時間は必要の目安。多量飲酒なら翌日運転しない前提で。