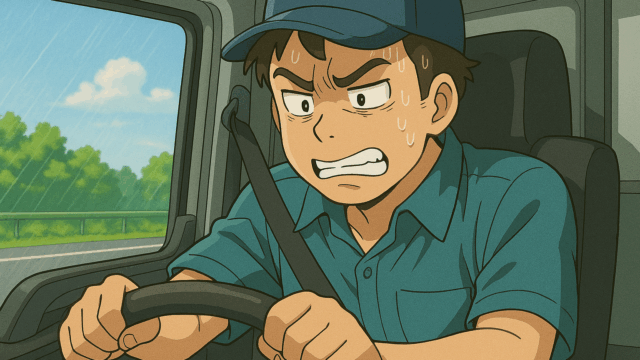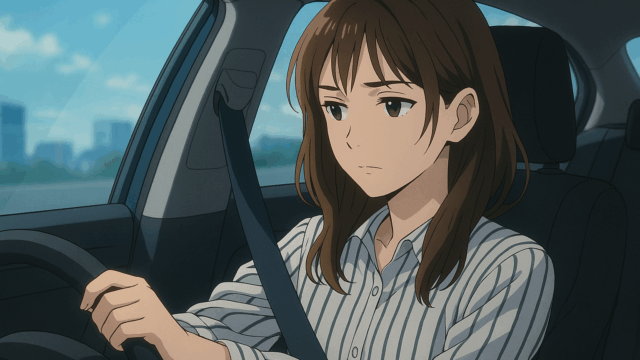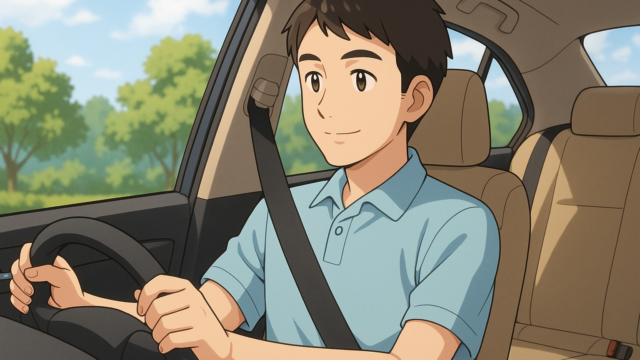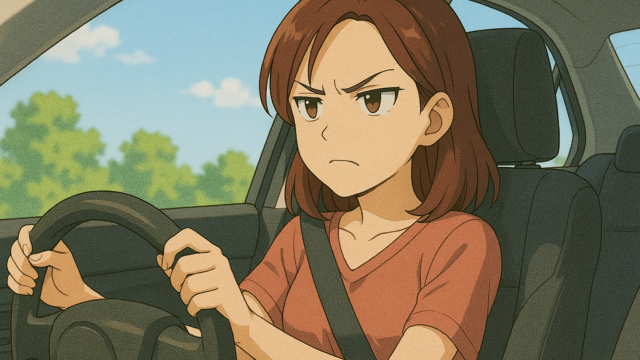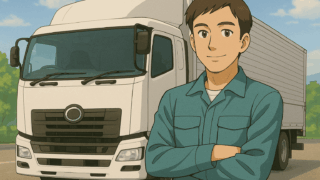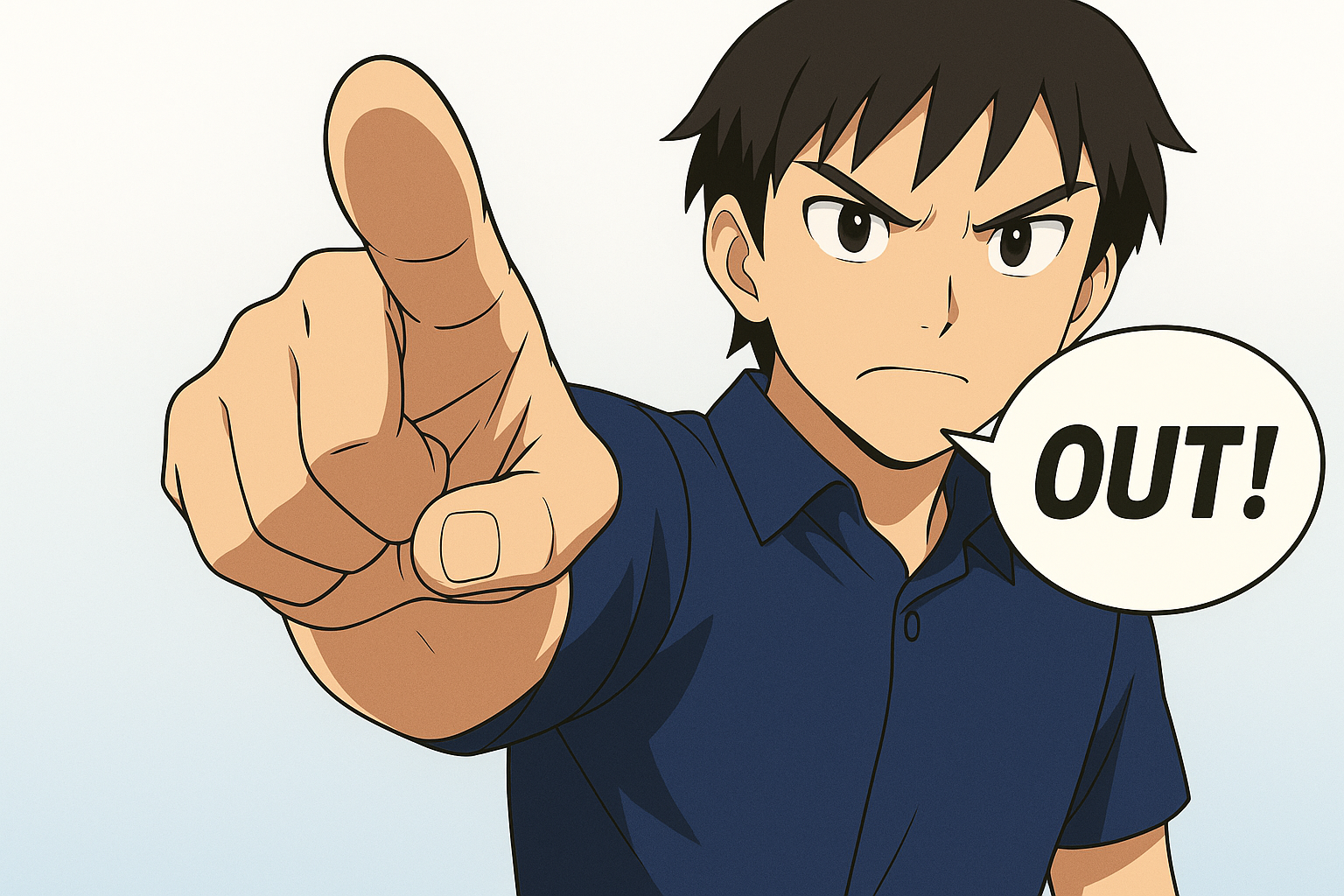初心者ほど煽り運転してしまうのは本当か?
その疑問、実はあながち間違いでもない。
煽り運転といえば、短気な中年男性が怒りに任せて…というイメージがあるかもしれない。
しかし現実には、免許を取ってしばらく経った「ちょっと慣れてきた段階のドライバー」が無意識に“煽り気味”な運転をしているケースが少なくない。
若葉マークを卒業したばかりの頃、誰しも少し気が大きくなる。
「もう初心者じゃない」「ちゃんと運転できてる」そんな自信が芽生える反面、過信と油断が入り混じるタイミングでもある。
この段階のドライバーがやりがちなのが「スピードの出しすぎ」だ。
高速道路やバイパス、信号の少ない郊外道では、制限速度を大きく超えるような速度を出してしまうことがある。
本人にとっては「流れに乗っている」感覚でも、後続車から見れば車間距離を詰めすぎていたり、不必要に追い越しを繰り返していたりする。
一方で、ベテランドライバーになると「速さ」よりも「楽さ」「安全さ」が運転の優先順位に変わってくる。
特に顕著なのが“車間距離”に対する感覚だ。
ベテランは無闇に車間を詰めない。
なぜなら「ブレーキを踏むのが面倒だから」だ。
ブレーキを踏むたびに減速・再加速の操作が発生し、燃費にも運転疲労にもつながる。
そこでベテランドライバーは、車間距離をあけて“クリープ現象”だけで減速し、スムーズな走行を維持しようとする。
その方が、時間的にも心理的にも余裕が持てるからだ。
つまり「車間距離を空ける=慎重派」ではなく、「合理的で効率的」な行動なのだ。
逆に、経験が浅いドライバーほど頻繁にブレーキを踏む傾向にある。
ちょっとした加速、前車の減速、信号の変化などに対してすぐに反応してしまう。
結果として、後続車に対する“減速のサイン”を多く出すことになり、状況によってはそれが“煽られている”と誤解されることもある。
また、前の車との距離を詰めることで「追い越しのチャンスをうかがう」心理が働きがちなのも、まだ余裕がないドライバーの特徴だ。
これは攻撃性ではなく“焦り”や“せっかちさ”からくる行動だが、周囲の車から見ればあまり印象は良くない。
実際、交通心理学でも「自信過剰な時期」と「運転技能の向上スピード」は必ずしも一致しないとされている。
つまり「慣れてきた」タイミングが、最も事故リスクの高まる時期でもあるということだ。
煽り運転は意図的な攻撃行為だけでなく、「未熟さからくる近距離走行」や「周囲への配慮のなさ」によっても発生する。
本人にそのつもりがなくても、結果として“煽ってしまっている”状態になることも多い。
だからこそ、自分の運転を振り返るクセを持つことが大事だ。
「自分は詰めすぎていないか?」
「無駄なブレーキをしていないか?」
「周囲にプレッシャーを与えていないか?」
それを意識するだけでも、運転は驚くほど変わる。
ベテランのように、車間距離を開け、クリープを使ってスムーズに走る。
それは単なる「安全運転」ではなく、「ストレスのない賢い運転」だ。
まとめ:煽り運転は“技術”よりも“余裕”の問題
煽り運転が起きる背景には、未熟さや焦り、自信過剰といった心理的要因がある。
とくに初心者を脱したばかりのドライバーは、その危ういバランスの中にいる。
一方、ベテランは“いちいち反応しない”運転をしている。
無駄に詰めない、ブレーキに頼らない、スムーズさを重視する。
それは「他人のため」ではなく「自分のため」の運転術だ。
若葉マークを卒業したその日から、本当の意味での“安全運転”は始まる。
煽ってしまう前に、自分の余裕を取り戻すこと。
それが一番効果的な“煽り運転対策”だ。